
戻る
目次(ここから次ページへ) 現在進行中!
下に般若心経現代語訳を付録としました。 ポップ調&八木幹夫氏訳
釈迦最後の教え (釈迦の言葉はわかり易いのだ!)
1 弟子たちよ、おまえたちは、おのおの、自らを灯とし、自らをよりど
ころとせよ、他を頼りとしてはならない。この法を灯火とし、よりどこ
ろとせよ、他の教えをよりどころとしてはならない。
2 常に聞き、常に考え、常に修めて捨ててはならない。もし教えのとお
りに行うなら、常に幸いに満たされるであろう。
3 相和し、相敬い、争いをおこしてはならない。水と乳とのように和合
せよ。
4 いたずらに悲しんではならない。世は無常であり、生まれて死なない
者はない。
5 仏の本質は肉体ではない。悟りである。肉体はここに滅びても、悟りは
永遠に法と道とで生きている。
和英対照仏教聖典 P19から
途中感想 2017.4.8
お釈迦様は仏教など作る予定は無かった。弟子たちが何代にも渡り伝えて
行く間に、小乗仏教や大乗仏教をお釈迦様の考えと関係なく作ってしまった。
親鸞さんも浄土真宗なんて作る希望は無かったそうだ。子孫と周囲の人が
「宗派」を作ってしまった。親鸞さんは死んだら、鴨川の魚に与えよと言って
た位だから。まあ、「宗派」を作り、儲かるシステム(利権と言う)を作らないと
布教も継続させるのは困難ですが。
和英対照仏教聖典のP49の仏の姿と仏の徳には、
1.姿や形だけで仏を求めてはならない。姿、形はまことの仏ではない。まこと
の仏はさとりそのものである。だから、
さとりを見る者がまことの仏を見る。とある。では、お寺に鎮座する仏様はな
んなのか?お釈迦さまの望みと、「仏教」は別物と考えた方が良さそうだ!
なんだーそうだったのか!
------------------------------------------------------------
古稀を迎えてあらためて「仏教書」を読み返す。
お盆と葬式しか縁がなく、お寺の廃業が増えているという。
人生の節目、節目で顔を出すが、イベント(七五三、お葬式、お年忌、お盆)でしか
身近なものとはなってない。
私も50年程前から、親鸞関連で歎異鈔の本を何冊か買ったが、積読に終わってい
る。あらためて深く読める齢となり、これからの社会には「真っ当な宗教」が必須と
考えて、このページに想いを並べてみたい。
これも終活と考えて「読もう」っと。
----------------------------------------------------------------------------------
先日、映画 「人生フルーツ」を見に行きました。
春日井市高蔵寺ニュータウンの一角に暮らす老夫婦のドキュメンタリー
「風が吹けば 枯葉が落ちる 枯葉が落ちれば 土が肥える 土が肥えれば 野菜が採れる」
(うろ覚えですいません)のナレーションに同感した映画でした。
良寛の「 たくほどは かぜがもてくる おちばかな 」を彷彿とさせる名言! 道元の本には、道元の
曹洞宗を一番引き継いでいる人が良寛のような紹介があったーーーー。 「炊くほどは 風が持て来る
落ち葉かな」 この生活だろうなーー。分を知った生活だな!
物の豊富な、欲望渦巻く現代社会に「何が必要か?何が大切か?」をチョットの時間考えさせてくれる
映画でした。
-----------------------------------------------------------------------------------
「仏教、本当の教え」(中公新書)より 数年前購入した本
購入した本の紹介コーナー(順次紹介)
 |
今日(2017.3.19) この本が届いた。 図書館でお経の本は無いかと探していたら、目に飛び込んだ本。お経を優しく 読める。 この本の作者が明治学院大学卒で、私と同じ年齢と知り、すぐ同じ大学卒の 同級生の家へ行き「この作者を知らんかん?」と聞いたら、「部が違うで知らん」 と言う。その同級生も70を迎えて仏教書を読んでいて、臨済が良いと勧められ た。奇遇と言うか、叩けよさらば開かれん! 犬も歩けば棒(お経)に当たる! |
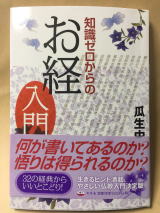 |
お経は座ってただ聞くもの・・・ですか? 手話通訳を仕事としていると、お葬式の通訳が困る。お経の間はただ座っている だけ仕事放棄しているように思われるので、「意味わからん。みんな大人しく聞い ている。」と通訳している。法然さんは仏教を貴族のものから、文字の読めない 庶民のものとする為、南無阿弥陀仏と唱えるだけで救われると簡略化して広めた が、お経は中国語のまま。意味のわからないお経はをかしいと思うのは私だけ? |
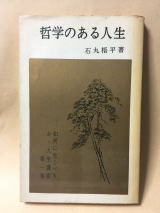 |
高校時代に購入した。本の題が気に入ったからだ。 題で購入したので、中身はあまり関心がなく未読の本となっている。 あらためて読んで見ようかと考えている。 暗闇の中でもがいていた時代を懐かしく感じている。 |
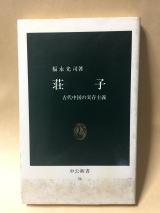 |
悩み深き青春時代に購入した。荘子は私の人生哲学となっている。 荘子の本は、稀有壮大な話しの中に、人を安心させるものがあった。 小さなことに拘ってはいけないよ!と言っている本。 息子に、この本を成人記念にプレゼントしたが、全く関心を示さなかった。 荘子には輪廻の思想は無い。死後の世界も大した問題としない。人間とはおの ずからこの世に投げ出された一個の生命と捉える。感銘し、指導いただいた本 の一つ! |
 |
歎異抄の本は継続的に購入した。 昭和44年出版だから22歳の頃の本。悶々とした時代に何かを掴もうとしてい た。これも購入はしたが未読の本となってしまい、70才で読み返している。 高校時代の先生が「本を買いなさい。本屋が喜ぶし、枕の横に置いておけば 自然と頭に入るから」と言われたのをはっきり覚えている。 |
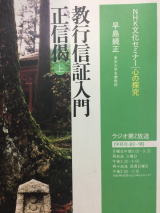 |
親鸞の教行信証入門 正信偈は仏壇や葬式で朗誦して途中まで暗記していた。 意味は解らないまま読んでいた。 あらためて意味を知りたいと思い読み返している。 |
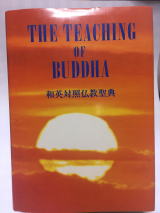 英語対照仏教聖典 |
ホテルに宿泊すると部屋の机の中に入っている本。 中学校時代の同級生からもらった。(偶然に!高齢になるとみんな仏さんに 近づくのか?) 仏教伝道協会出版だから宗派に関係なく、釈迦の話した言葉 が載っている。 経典とは異なって、読みやすい話になっていいる。 英語併記だから、どんな訳になっているか興味深々。 これを学生時代に知っていれば、私は英語ペラペラになっていた。多分! 仏教の読み直しには最適な本。この本にはお釈迦様の生の説法が多く 載っているようだ。 |
付録
|
|
日本語で読むお経 松柏社より 「偉大な智慧の完成を説いたお経」 真実の世界をありのままに見ること が出来る菩薩よ あなたは深い智 慧の光で、人間の心と身体を含め この世にあるものはすべて空なるも のだと深く見通され、いっさいの苦し みやわざわいから自由になられま した。 賢きものよ(舎利子よ)、次のことを知 りなさい。肉体とは空なるものであ り、そもそも空なるものが肉体なの です。 さらにいえば、肉体は存在しないも のであり、そもそも存在しないものが 肉体なのです。 物質でありながら物質でないもの、 存在しないものでありながら存在する もの。こうしたことを受け止とる心や 五感のうごきもまた同じように空なる ものなのです。 賢きものよ、次のことを知りなさい。 あらゆる存在は空なるものです。 生じたり滅びたりするように見えて も、生じもしなければ滅びもしないの です。 汚れもしなければ清らかになることも ないので、増えることも減ることもな いのです。それゆえに空なる世界で は、もはや肉体(物質)もなく、それを 感じとる心や五感もないのです。 目で見ることなく、耳で聞くことなく、 鼻で嗅ぐこと舌であじわうことなく、 身体で触れることなく、心で受とめる こともないのです。 私たちが心や五感で感じとるその 対象の世界もなければ、感じとる 私たちの心や五感の世界もないの です。 欲望にまどわされて闇に迷うことも なければ迷いの闇がすべてなくなる こともないのです。さらにいえば老い ていく苦しみもなく、死んでいく苦しみ もなく、また老いや死の苦しみがすべ てなくなるなこともないのです。 そもそも苦しみはないのです。苦しみ の原因もなく、苦しみの消滅もなく、 苦しみをなくす方法もないのです。 知るということもなければ、得るという こともないのです。そもそも得るべき ものはもともとないからです。すべて はうつろう空なる世界です。 ひたすら道を求めつづけてきた菩薩 はこうして深い智慧をさとることによ り、心になんのこだわりもなくなり ます。 こだわりがなくなれば、不安や恐れは たちどころに消え去るのです。心の乱 れ、ものごとを正しく見ることのできな かった迷いを遠去け、ついに究極の 涅槃(さとり)をきわめたのです。 過去から現在、未来にわたっておられ るさまざまな仏もこの偉大な真理を 示す智慧により菩薩と同じように素晴 らしい悟りを得ることができたのです。 ですから、賢きものよ 知りなさい。 この智慧の究極の完成、この大いなる 霊力をもつみことば、世界をあまねく 照らす光のみことば、この上なくすぐれ たみことば、比べるもののないみこと ば、すべての苦しみや煩悩を取り除き、 真実の、けっして偽りのないもの、至高 の智慧のみことばゆえに、その言葉は 次のように唱えます。 ギャーテー ギャーテー ハーラーギャーテー ハーラーソーギャーテー ボージーソーワーカー (八木幹夫氏訳) -------------------------------- 中村元氏訳呪文 往き往きて、 彼岸に到達せる悟りよ、 幸あれ。 |